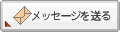2010年09月24日
レコード盤
沖縄に住んでいた頃はその気候のせいかプログレッシブ・ロックをほとんど聴かない日々が続いていたが実家に帰ってみると、しかも季節が冬だったこともあり、俄然プログレを聴きたくなったのは自分でもおかしかった。 …やはりプログレを聴くには忍耐力が必要なのだろうか。 沖縄の暑さは体力だけではなく忍耐力まで奪っていくのだ…
実は沖縄にはイザという時のためにレコードプレイヤーこそ持って行ったもののアナログ盤は1枚も持って行かなかった。 それは湿気によるカビと海風による塩害を恐れたからである。 じゃあCDなら大丈夫かと言われれば「そうだ!」とは言えないが、アナログ盤は貴重な物も多かったし、もしもダメになった時に取り返しがつかないというリスクが大きかったから。 ということで実家に大量のアナログ盤を置いてきたのだった。
「愛しいアナログ盤たちよ♪」
実家に戻ってまずチェックしたのはこの子達だった。 閉め切った部屋に放置してて、それこそカビは生えていないか? 暑さで曲がってはいないか?と点検した。 ジャケットを眺めてはその音を思い出し、CDで持っていないアルバムはターンテーブルに乗せて一枚一枚聴く日々がしばらく続いた。
しかしCDでも持っていて沖縄でもずっと聴いていたアルバムが1枚ある。 それがパヴロフス・ドッグの1stアルバム『PAMPERED MENIAL』だ。

針を落とした瞬間からラストまで美しさと激しさが見事に調和した音美学が構築されている名盤である。 ボクの音楽用宝箱に大切にしまっておきたい一枚だ。
このバンドの大きな特徴といえばやっぱりDAVID SURKAMPのハイトーンボーカルであろう。 よくレビューなどを見ると“RUSHのゲディ・リーのような…”とか書いてあるけど、ボクはそれにはあまり賛成していない。 DAVIDのボーカルはもっと細かいヴィブラートがかかっており、声質的には浜田麻里さんに近いと思っている。 そう、彼の声帯は女性のそれに近いんだと思うんです。 でなきゃ、この危うさ(先ほど記述した“はかなげ”“切なげ”さ)は表現できないと思う。
ボクはこのアルバムでの最大の聴きモノは1曲目の「JULIA」だと思ってます。
静かな優しいタッチのピアノから始まるバラードがアルバムのトップを飾るんです。 彼等の相当な自信がそこに見えます。 メロトロンがさりげなくバックを彩ります。 ボクは彼等のメロトロンの使い方が好きなんですね。 あまりにも曲にハマりすぎてつい聴き逃してしまうくらいのさりげなさ。 いや、もちろんメロトロンという楽器を知っている人には「メロトロンの洪水だぁ~」みたいな表現をしたくなるんでしょうけど…。 間奏ではこれまた繊細なフルートソロが聴けます。 哀しげで涙腺がゆるみそうな名曲です。
この他にも「LATE NOVEMBER」や「THEME FROM SUBWAY SUE」などの素晴らしい曲が散りばめられています。 アルバム全体を総括すると、このバンドはどこか愁いを帯びていて常に後ろ髪を引かれる雰囲気を持っているということかな? とても繊細で優しく、ROCKの持つ美しい面を凝縮した70年代の代表的な名盤だと断言できます。
さて、「Julia」と言えばプログレの御大ピンク・フロイドもサイケデリック(アートロック)時代に「Julia Dream」(邦題:夢に消えるジュリア)というナンバーを残している。 こちらも静かにアルペジオを奏でるアコースティックギターの上にフルートをかぶせた素朴な編成で淡々と歌われていく。 もちろん時代が時代だけに中間部からはエコーを効かせたサイケな効果音やメロトロンが加わりある種トリップ的な感覚に浸ってくる。 とはいえ主旋律がマイナー調で美しく素朴なために妙な切なさとやるせなさが後を引く。
それはそうと…外国では「Julia」という女性の名はちょっと悲観的なイメージがあるのだろうか。
(ちなみにビートルズも「Julia」という曲を作っているが、やはりそんな感じの曲調だったりする)

実は沖縄にはイザという時のためにレコードプレイヤーこそ持って行ったもののアナログ盤は1枚も持って行かなかった。 それは湿気によるカビと海風による塩害を恐れたからである。 じゃあCDなら大丈夫かと言われれば「そうだ!」とは言えないが、アナログ盤は貴重な物も多かったし、もしもダメになった時に取り返しがつかないというリスクが大きかったから。 ということで実家に大量のアナログ盤を置いてきたのだった。
「愛しいアナログ盤たちよ♪」
実家に戻ってまずチェックしたのはこの子達だった。 閉め切った部屋に放置してて、それこそカビは生えていないか? 暑さで曲がってはいないか?と点検した。 ジャケットを眺めてはその音を思い出し、CDで持っていないアルバムはターンテーブルに乗せて一枚一枚聴く日々がしばらく続いた。
しかしCDでも持っていて沖縄でもずっと聴いていたアルバムが1枚ある。 それがパヴロフス・ドッグの1stアルバム『PAMPERED MENIAL』だ。

針を落とした瞬間からラストまで美しさと激しさが見事に調和した音美学が構築されている名盤である。 ボクの音楽用宝箱に大切にしまっておきたい一枚だ。
このバンドの大きな特徴といえばやっぱりDAVID SURKAMPのハイトーンボーカルであろう。 よくレビューなどを見ると“RUSHのゲディ・リーのような…”とか書いてあるけど、ボクはそれにはあまり賛成していない。 DAVIDのボーカルはもっと細かいヴィブラートがかかっており、声質的には浜田麻里さんに近いと思っている。 そう、彼の声帯は女性のそれに近いんだと思うんです。 でなきゃ、この危うさ(先ほど記述した“はかなげ”“切なげ”さ)は表現できないと思う。
ボクはこのアルバムでの最大の聴きモノは1曲目の「JULIA」だと思ってます。
静かな優しいタッチのピアノから始まるバラードがアルバムのトップを飾るんです。 彼等の相当な自信がそこに見えます。 メロトロンがさりげなくバックを彩ります。 ボクは彼等のメロトロンの使い方が好きなんですね。 あまりにも曲にハマりすぎてつい聴き逃してしまうくらいのさりげなさ。 いや、もちろんメロトロンという楽器を知っている人には「メロトロンの洪水だぁ~」みたいな表現をしたくなるんでしょうけど…。 間奏ではこれまた繊細なフルートソロが聴けます。 哀しげで涙腺がゆるみそうな名曲です。
この他にも「LATE NOVEMBER」や「THEME FROM SUBWAY SUE」などの素晴らしい曲が散りばめられています。 アルバム全体を総括すると、このバンドはどこか愁いを帯びていて常に後ろ髪を引かれる雰囲気を持っているということかな? とても繊細で優しく、ROCKの持つ美しい面を凝縮した70年代の代表的な名盤だと断言できます。
さて、「Julia」と言えばプログレの御大ピンク・フロイドもサイケデリック(アートロック)時代に「Julia Dream」(邦題:夢に消えるジュリア)というナンバーを残している。 こちらも静かにアルペジオを奏でるアコースティックギターの上にフルートをかぶせた素朴な編成で淡々と歌われていく。 もちろん時代が時代だけに中間部からはエコーを効かせたサイケな効果音やメロトロンが加わりある種トリップ的な感覚に浸ってくる。 とはいえ主旋律がマイナー調で美しく素朴なために妙な切なさとやるせなさが後を引く。
それはそうと…外国では「Julia」という女性の名はちょっと悲観的なイメージがあるのだろうか。
(ちなみにビートルズも「Julia」という曲を作っているが、やはりそんな感じの曲調だったりする)

*当サイトに掲載されている全ての画像、文章等の無断転写、転載を禁じます。
Copyright(C) 2000-2012 Groovus! All Rights Reserved.
Posted by ロマネスク at 15:29│Comments(0)
│音楽